特徴
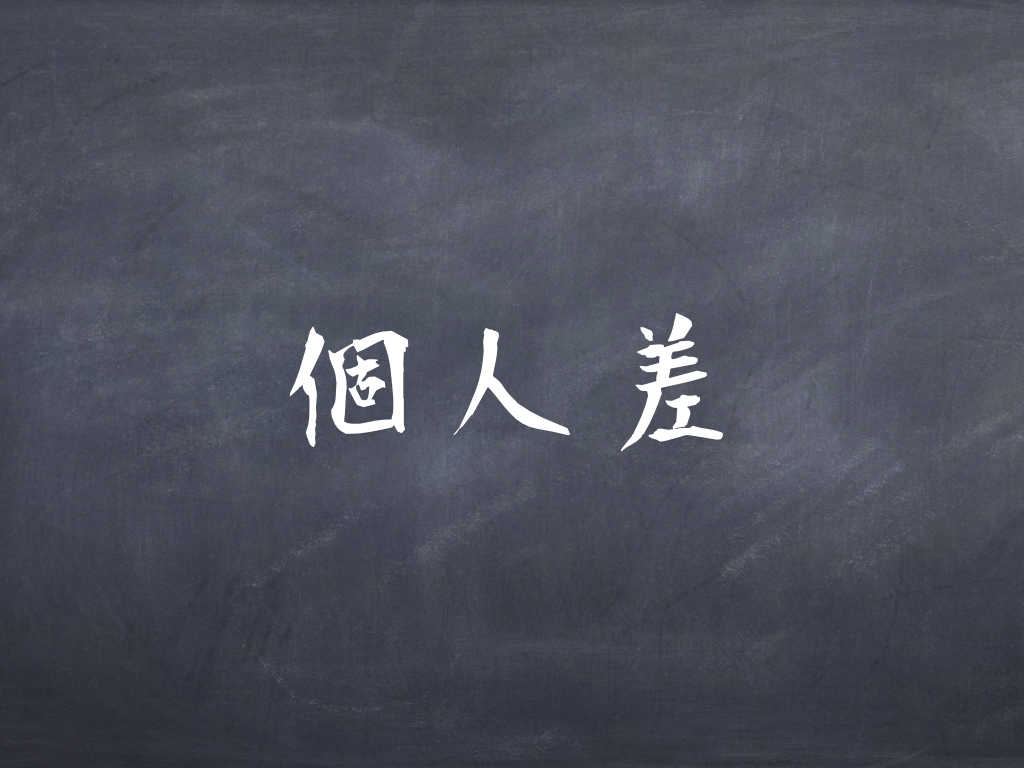
一般的に、小学生は他の年代に比べて、『個人差』がとても大きいため、周囲の大人もそれを意識しながら、接する必要があります。
たとえば、四年生くらいから算数を中心に勉強が難しく感じる子が目立ち始めますが、中には健闘むなしく、どうしても苦手から抜け出せないケースもあります。一生懸命やっているんだけど、イマイチわかってなさそうだったり、あるいは、そもそも出来ないことにショックを受けている様子もなく、あっけらかんとしている・・・。そんな状況を見て、周囲の大人はどうしても「努力や危機感が足りないのではないか?」と考えがちで、我が子可愛さに焦りも相まって、勉強を無理強いしてしまうことがあります。
たしかに、子どもは大人と比較して、はるかに柔軟で従順です。しかし、だからといって、無理を強いてしまうと、その場では怖くて必死になるかもしれませんが、大人の居ないところではやがて怠けるようになりますし、雷を落とせば落とすほど恐怖心も薄らぎ、最終的には何を言っても聞かない子の出来上がりです。
たとえ真面目なお子さんに対してであっても、多くの場合、こうしたアプローチは有害です。「自分はいくらやってもできないダメな子なんだ・・・」と、自己肯定感の喪失に繋がってしまったり、「何をしているのか全然わからないけど、とりあえず怒られないことが大切。答えを覚えて、わかったフリをしておけば良いだろう」といった誤った勉強観を醸成するきっかけになってしまったりします。
また、もしも無理強いが幸運にも(あるいは長い目で見れば不運にも)うまく行ったとしても、その先にあるのは『自分の意見を持てず、他者の顔色ばかりを伺う人生・・・』ということにもなりかねません。
そもそも、小学生時点での遅れの原因は『脳の発達タイミング』に由来することが多く、したがって、大人としては主に二つのことを念頭に、子どもを補助してあげる必要があります。
第一に『他の子と比べないこと』です。「周りの子は今これだけ出来ているのだから・・・」と心配になる気持ちはわかりますが、それを子どもにぶつけても改善につながることはありません。必要なのは、他の子と比較するのではなく、過去のその子自身と比較すること。つまり、本人がしっかり努力し、その結果少しでも改善が見られたのであれば、それをしっかり認めてあげる必要があるのです。
第二に『長い目で見てあげること』です。お子さんはまだ小学生です。ゴールは『今この瞬間』ではありません。大切なのは10年後の可能性をいかに最大化するかです。我々大人は、そうしたより広い視野で物事を見てあげなくてはなりません。それが出来るからこそ、我々は大人なのですから。
もちろん、努力の価値を否定するわけでは決してありません。しかし、近視眼的な恐怖心から、大人側が子どもを追い詰めるようになってしまってはお終いです。「雨垂れ石を穿つ」とも言います。大人から見れば小さな努力だとしても、続けていれば挽回のチャンスはきっと巡ってきます。今はその子だけを見てあげて、焦らず気長に、しかし絶えることなく、支援してゆきましょう。
目標
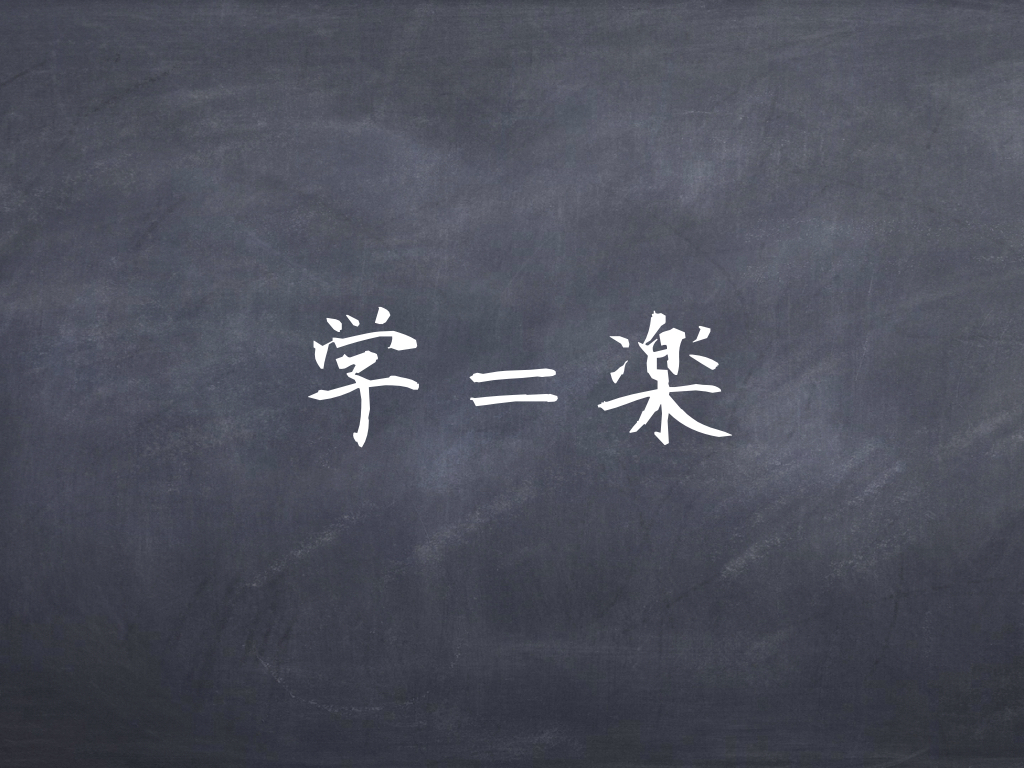
青稲塾が小学生を指導する上で目標としているのは『学ぶことは楽しいことだ!』という事実に気付いてもらうことです。
小学生の間は『個人差』が非常に大きいことはすでに述べた通りですが、『楽しさがわかり、好きになったものに対しては、並々ならぬ集中力を発揮する』というのも、この年代の特徴です。(その反面、楽しくないことには集中できないという特徴も顕著ですが・・・。)
お子さんの人生が小学生時点の出来で決まることはありません。勉強の楽しさを知ることは、その後の人生において大きなアドバンテージにもなります。今後の伸びしろを大きくするためにも、本当の意味で「勉強は楽しいんだ!」ということに気づいてもらいましょう!!
改善案
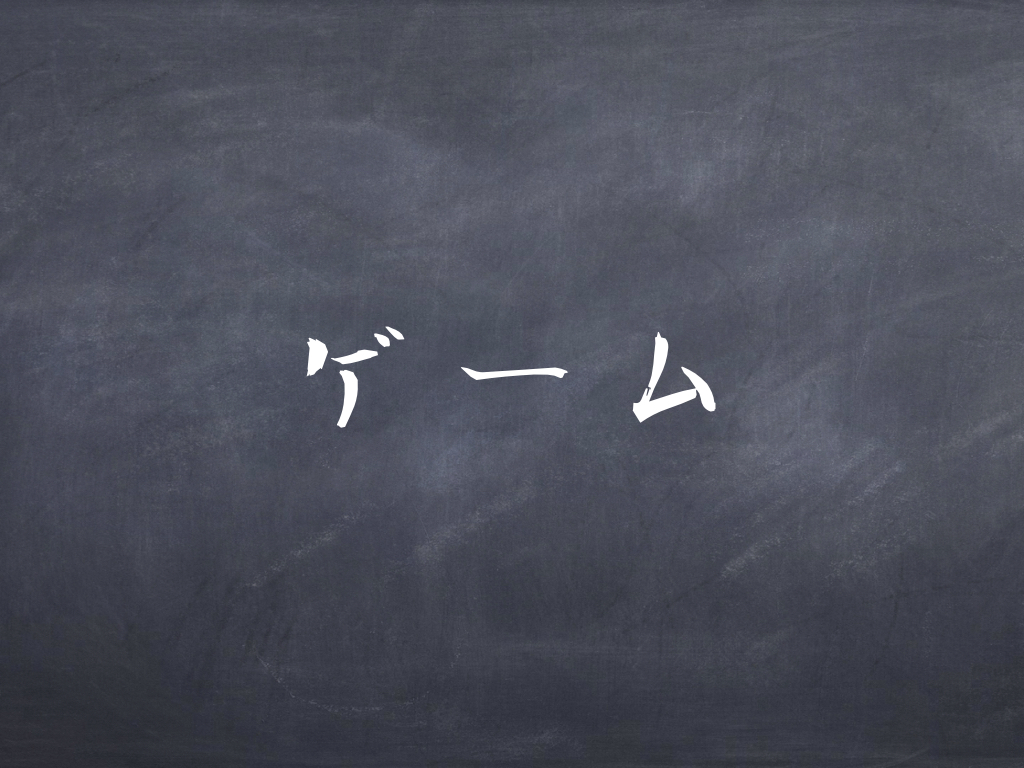
何かに対して「楽しい!」と感じるのは、どのような時でしょうか?多くの子どもが日々楽しそうに、自発的に取り組んでいるものにゲームがありますね。なぜ、ゲームはあれほどまでに子どもを虜にするのでしょうか?
- 行動に対する、派手で目を引く即時的反応
- 序盤は比較的スラスラ。実力に合わせて徐々に難易度が上昇
- 難関に差し掛かるとボーナスで強力な武器を獲得
このように、『フィードバックが魅力的で即時性が高いこと』と『難易度設定が卓越していること』といった面が、ゲームの持つ中毒性の一端を担っていると言えそうですが、これらの性質は学習指導にも活かすことができます。たとえば・・・
- 出来なかったことが出来るようになったら、即座に惜しみなく褒める
- スラスラ解ける簡単な問題から始め、実力に応じて徐々に課題の難易度を上げてゆく
- 考えても現時点の実力では難しそうな場合は、最高のタイミングで最高のヒントを与える
青稲塾では、このように、ある種の『ゲーム性』を取り入れることで、楽しんで勉強を継続してもらえるよう心がけています。
