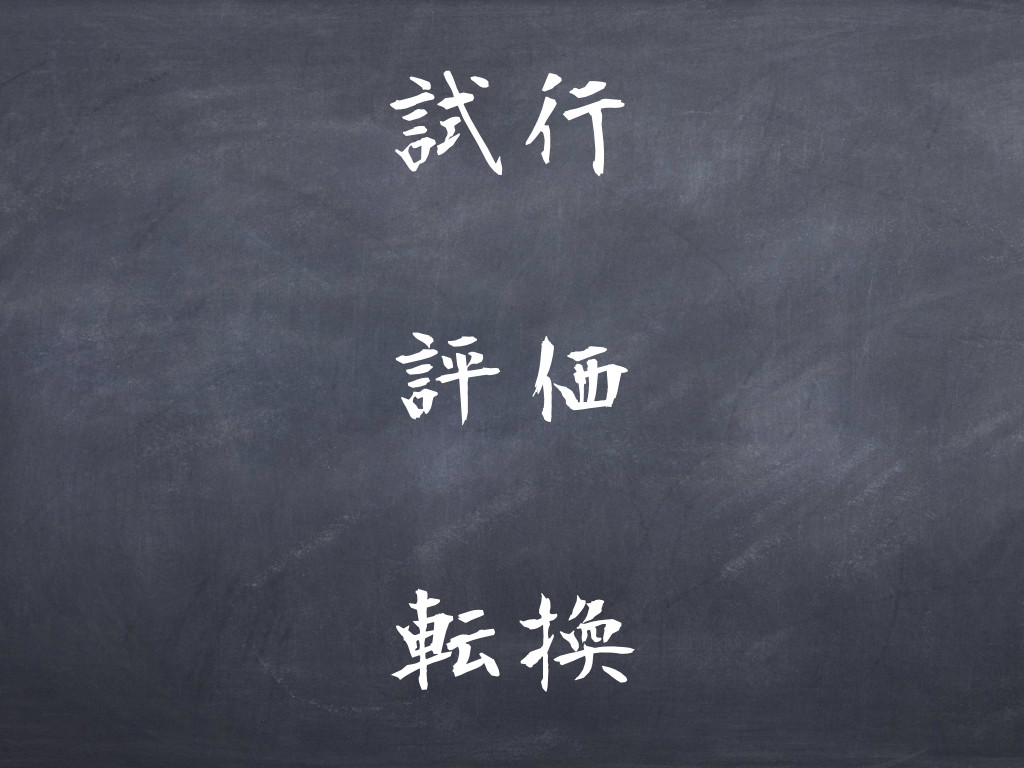
どれほど時間を費やし、『計画』に万全を期そうともやはり計画は計画でしかない。プランニングは必須だが、立てたプランがそのまま上手くいくことは稀なのだ。
重要なのは予定から外れた際の軌道修正。『試行・評価・転換』の3つをキーワードに『修正』プロセスを回し続けよう。
『試行』(修正の一)
勉学に限った話ではないが、新しい事柄への挑戦を求められたとき、我々はどうしたって及び腰になってしまう。経験の少なさゆえに、挑戦に対する見返りをありありと思い描くことは難しく、時に代償を過剰に見積もることさえしてしまう。その結果、動き出す前に完璧な計画を追求し、時間を際限なく浪費し続ける。「リスクヘッジ」といえば聞こえはいいが、その実はただの失敗恐怖症。目的地までの道のりは一ミリたりとも変わることはない。
『試し』にやってみよう!
どれほど素晴らしい『計画』を立てても、実行しなければ目的地にたどり着くことはない。しかしまた逆に言えば、どれほどゆっくりな歩みでも、それを止めさえしなければ、いつかは目的地にたどり着くことが出来るのだ。歩いていれば時には走る気にもなるかもしれない。とにかく一歩を踏み出そう。それだけで口先だけの有象無象と一線を画すことができるのだ。
とにかく、始めよう!!!
オブシアンキーナー効果というのがある。「未着手品は嫌厭しがちだが、未完成品は完成品に仕上げたい気持ちが働く」という人間心理を、発見者にちなみそう呼ぶ。
渋っていた部屋の掃除も一度始めてみるとあれこれ気になり始めて、なかなか区切りがつけづらくなってしまった経験が、あなたにもないだろうか?
まずは二分間、それも難しいなら一分間。いや、その半分だって構わない。とにかく取り組んでみるのだ。そうすれば『未着手品』は『未完成品』へと変化し、いつの間にやらページを捲る手を止める方が難しくなる。これを狙うのである。
もし二分間やっても、それでもやる気が生じないのであれば違う作業に移ればよい。それさえも難しいなら休憩を取っても構わない。
とにかく動き出そう!!!
『評価』(修正の二)
『試行』の結果は『日・週・月の終わり』に『評価』することを徹底しよう。その際には客観性が重要となる。『行動記録』を日々忘れずに取得しておきたい。
『日次レビュー』は『短期計画』と当日分の『行動記録』をベースに行う。両者を比較し、設定した全ての『タスク』について達成できたかを確認し、もし未達成のものがあるならその原因を考えよう。
未達成の場合、その原因は以下のように、大きく二種に分類できるだろうが「いつ・どこで・何を」行ったのか、または行わなかったがゆえに失敗したのか、原因を具体的に究明する姿勢が大切である。
- 原因その一
所要時間の設定ミス - 原因その二
干渉行動
※やるべき『タスク』に干渉してその達成を難しくする行動。「動画を見続けてしまう」など
また「良かった点」についても考え、メモを取っておくと、今後のモチベーションの向上につながるだろう。
『週次レビュー』は『中期計画』を元に行う。『Target』の進捗状況を確認し、未達成ならその原因を考える。大きく分類すると原因は下記二点のいずれかになるはずだが、『短期計画』などを参考にして、さらなる具体化を行って欲しい。
- 『タスク』の未達成
- 『Target』の細分化ミス
『月次レビュー』では『長期計画』をベースに『Objective』の達成を確認する。 未達成の原因は大きく分類すると下記二点のいずれかになるはずだが、『中期計画』を参考にし、失敗要因のさらなる具体化を行うべし。
- 『Target』の未達成
- 『Objective』の細分化ミス
さて、ここで『目標の細分化ミス』という概念について触れておこう。
たとえば「河合塾全統記述模試英語偏差値60突破」を『Objective』に設定し、それを達成するための『Target』として「シス単の95%以上の単語に関して、一秒以内に和訳が言えるようになること」を設定したとする。しかし、その『Target』を達成したにも関わらず、「偏差値60突破」という『Objective』が達成出来なかった。この場合、その原因はどこにあるのだろうか?
このような場合に、その原因として考えうるのが『目標の細分化ミス』である。『Target』は『Objective』達成のための小目標として、『タスク』は『Target』達成のための具体的行動(課題)として設定するわけだが、学習初期においては『ObjectiveやTarget』を達成するために必要十分な条件を把握する能力が不足しているため、このような細分化が上手く行かないことが多いのだ。
とはいえ、まだ時間が残されているのであればこれを過度に恐れることはない。思いつく限りの弱点を考え、次の『Target (またはタスク)』を設定し、その一つ一つを潰してゆく。そうすれば、多少の遠回りにはなるかもしれないが、やがては自然と『Goal』に辿り着くことになるだろう。
さらに、本当に基礎的な語彙に抜けがなくなったのであれば、今や「どこが弱点であるか」についても以前に比べてずいぶん目端が利くようになっていることだろう。この過程を繰り返してゆけば、徐々にではあるが確実に問題点を把握する力にも向上が見られるのだ。倦まず弛まず、経験を積み上げ続けよう。
それでもなお一人では心配な場合や、残り時間が少ない場合には『分析』の節でも説明したように十分な『実力明確化』を行った後で信頼に足る人物に相談するとよいだろう。
青稲塾では、『Daily・Weekly・Monthly-Review』のそれぞれを『スタディシート』(『Project』・『Chart』・『Schedule』)を活用し、行っている。
『転換』(修正の三)
適切に自己の状況を『評価』し、問題点を明確化することに無事成功しただろうか?
以下によくある問題点を四つ並べてみた。読者諸君の抱える問題もこれらの内にあるのではないだろうか?
- 目標の細分化が苦手
- 時間効率が悪すぎる
- 長時間集中力が保たない
- つい遊びを優先してしまう
特に最後の「つい遊びを優先してしまう」という悩みを、学習初心者からよく聞く。勉強を新たに決意した者の内、決して少なくない割合が三日を過ぎたあたりから、早ければ初日から絶望に打ちひしがれることになるわけだが、何故他ならぬ自分自身を制御するだけのことが、かくも難しいのだろうか。これは残念なことに我々人間の本質に起因する。
人間は本質的に『き・な・こ』である。
(気まぐれ、怠け者、根性なし)
我々の自我など、まさにきなこのように、吹けば飛ぶような存在なのだ。まずはこれを受け入れなければならない。失敗の多くは、これを無視して「自分になら出来るに違いない!」と『きなこ』な精神にすべてを丸投げしてしまうという暴挙に起因するのである。的確な手を打つために必要なのは、まずは『きなこ』であること認知すること。そして次に「この吹けば飛ぶような自我をいかに制するべきか」という視点に立つことである。
行うべきは『転換』である。
必要にも関わらず、ついサボってしまう『タスク』や、それと競合する、ついやってしまう不必要な行動(『ライバル』)について種々の要素(『魅力・抵抗・引金・反応』)を検討し、捉え方を変化させることによって突破口を開こう。
- 『魅力』・・・『行動』自体に発する行動促進要素
- 『抵抗』・・・『行動』自体に発する行動抑制要素
- 『引金』・・・『行動』に先行する行動促進要素
- 『反応』・・・『行動』に後続する行動促進要素
ここで言う『魅力』とは、特定の『行動』自体に発する、それを促進する要素のことである。『タスク』の達成率を高めたいときには以下の項目から該当するものが増えるよう、『ライバル』の回避率を高めたい場合には該当する項目が減るよう、工夫を施し、行動の捉え方が変化するきっかけを作り出そう。
- 『Goal』に接続している
- 完了で達成感が得られる
- 期限に関し選択権がある
- 場所に関し選択権がある
- 方法に関し選択権がある
ここで言う『抵抗』とは、『行動』自体に発する、その抑制要素のことである。『タスク』の達成率を高めたいときには以下の項目から該当するものが減るように、『ライバル』の回避率を高めたい場合には該当する項目が増えるように、工夫を施そう。
- 手順が具体性を欠いている
- 開始に労力が必要である
- 完了に労力が必要である
- 流用可能な成功体験がない
- 同時進行の行動がある
ここで言う『引金』とは、『行動』に先行し存在する、その促進要素のことである。『タスク』の達成率を高めたいときには以下の項目から該当するものが増えるように、『ライバル』の回避率を高めたい場合には該当する項目が減るように工夫を施し、行動の捉え方に変化をつけよう。
- 高確率で先行する要素がある
- 先行要素の誘因性が高い
- 先行要素が備忘性を持つ
- 先行要素が他者性を持つ
『反応』も『行動』の促進要素であるが、『引金』との違いは行動に後続して存在するという点である。『タスク』達成率を高めたいときには以下の項目から該当するものが増えるよう、『ライバル』の回避率を高めたい場合には該当項目が減るよう、工夫を施そう。
- 高確率で後続する要素がある
- 後続要素が魅力的である
- 後続要素が即時的である
- 後続要素が他者性を持つ
このように、『魅力・抵抗・引金・反応』の四つの切り口から行動を分析し、不十分な『タスク』と過剰な『ライバル』に対処するというのが基本方針となるのだが、しかし、注意すべき点がある。すなわち「『転換』を一度行った程度では、あらゆる『行動』が適正化されるわけではない」ということである。
行動にまつわる大半の問題は行動主体、つまり、読者諸君がこれまでに積み上げてきた習慣に大きく由来する。そして、習慣とは、行動の蓄積の末に固定化された個々人の行動規則のことを言うのである。それが良いものであれ、悪いものであれ、長年かけ形成してきた思考・行動パターンは強い力であなたを縛り上げる。それは、どだい、一朝一夕で覆せるものではありえないのだ。
問題点を認識し、手を加え、試し、それを評価し、問題点があればまた手を加える。このような過程を繰り返す中で、理想的な行動を自己に浸透させてゆく。望ましい行いを新たな習慣として、古い習慣に上書きしてゆく。地道で途方も無いと感じるかもしれないが、『そうありたいと願う自分』になるためには、この他に方法はないのである。もちろん容易に変化など起こらない。しかし、だからといって絶望に足を止めてはならない。人間は『きなこ』である。だがそれでも、絶え間なく行動を続ければ、ゆっくりでも確実に成長するのだ。
『試行・評価・転換』の循環を常に維持し続け、『理想的な自分』を獲得しよう。
なお、青稲塾では『Change』を活用し、『転換』を行なっている。
