
どの教科でも高得点を取る人がいる一方で、どの教科でも赤点ギリギリな人がいる。一体、両者の違いはどこから生じるのだろうか。
モノを教える立場にあると「あの人とは頭の出来が違うから・・・」というセリフにたびたび遭遇する。我々人間は『目にしたもの』をこそ、知らず識らず思考の土台として自己に位置づけてしまう生き物であり、それに加えて、『できる人』がそうあり続けるために日々頭の中で行っていることや、それに費やしてきた、そして今まさに現在進行形で費やしている労力は視覚によっては捉えがたいのである。すると、その結果、初学者が彼我の戦力差について分析を行うとき、それはしばしば『地頭の良さ』を主軸としたものとなる。曰く、「成績の良いアイツもやっている教材は自分とさして違わないみたいだ。・・・ということは、アイツの成績が良いのも、逆に自分がなかなか伸びないのも、結局は地頭のせいに違いない・・・」というわけである。
気持ちはよく分かる。しかし、彼らが前提としがちな、また残念なことにしばしば『言い訳』としても利用されがちなこの認識は、現実を正しく映し出すことが出来ているのだろうか?
答えは「否」である。たしかに『地頭の違い』というやつも、学習上の優劣を分ける要因として無視できない働きを行う。しかし、優れた結果を残す者とそうでない者とを分けるのは、そうした先天的要素だけに留まらない。『学習観・思考習慣』もまた決して無視できない働きを行うのだ。
このシリーズでは、まさにそうした『出来る子の学習観・思考習慣』にスポットライトを当ててゆく。ぜひ隅々まで目を通し、読者諸君の『自ずから学びゆく力』を向上させるきっかけとしてくれることを願う。
学びの目的地(仮)

それでは本題に入ろうかと思うが、まずは向かうべきゴールについてはっきりさせておきたい。そこで、初めにひとつ質問に答えて欲しい。
あなたは何のために
日々勉強を続けるのだろうか?
数日後の小テストのため?来週の定期試験のため?それとも来月に開催される英検のためだろうか?もしかしたら数年後の東大合格を勝ち取るためという人も読んでくれているかもしれない。
このように学習主体に応じ、その学習目標は様々であり、したがって、より具体的なレベルで話をするのであれば、それぞれの目標に対し、それに特化した無数の効率的な勉強法がありうるだろう。
しかし、世にある無数の学習目標に対してある程度の抽象化を許容するのであれば、これは学習を継続する者の大多数にとり、意味ある助言たり得るのではなかろうかと思う。そこで、以降では学習者の『学びの目的地』を以下のように仮置きし、それに必要となる要素について述べてゆく。
『目標達成に対して十分な実力を
期日までに養成すること』
なお、日々学び続ける者の中には知識獲得の楽しみを純粋に原動力とし、したがって試験を受ける予定のない、すなわち期日を持たない学習者も当然存在する。
もし、あなたがそうした己の好奇心にのみ突き動かされ、特に時間対効果を考える必要なく学習を進める者である場合には、この先の説明の中に一部不要な箇所もあろうかと思う。そうした部分にあっては各自の裁量と責任によって読み飛ばしてもらって一向に構わない。
実力最大化のために

では、次に『目標達成に対する十分な実力を期日までに養成する』ための必須要素について考えてゆこう。
まず第一に、期日時点の実力が『現時点での実力と今後の伸びの和』によって表されるということに議論の余地はないだろう。では『今後の伸び』を決める要因は何だろうか?
『可処分時間』と『効率性』である。
使える時間が多ければ多いほど有利であること、そしてたとえば一時間につき五つの知識を理解するのと、十をモノにする場合とでは、最終結果に大きな差がつくことにも、特段反論の声は上がらないと思う。
問題はここからだ。では、この『効率性』というものは、具体的にどのような方法によって高めることができるのだろうか?意識すべきことや、選択すべき行動はどのようなものになるのだろうか?
青稲塾では、こうした問いに対し、「学習プロセスをその段階ごとに『段取・習熟・定着』の三要素に分解し、それぞれを効率化するという手法で、総合的に高度な効率性を実現する」という解を提示する。
段取の極意

ところで、勉強は見知らぬ土地を旅するのに似ていると言えないだろうか。歩み続ければいつしか思わぬ景色を見せてくれるが、限られた時間において望む光景を堪能したいと欲するならば、事前の『下調べ』は不可欠である。では・・・
下調べさえ完璧ならば十分か?
当然そんなことはありえない。集めた情報をもとに『実現可能かつ最短ルートの計画』を策定し、次にそれを頼りに実際に足を動かしてみる。ある程度進んだらそれまでの道のりを振り返り、再度目的地と自己の位置関係を把握し、ここで実際と計画のズレが判明すれば、それを材料に計画を修正し、正しい方向へ次の一歩を踏み出す。そしてまたある程度進んだら、それまでの歩みを確認し、必要があれば計画に修正を加え・・・。
与えられた時間内で目的地へたどり着くことを確実なものとしたいのであれば、このように『分析・計画・修正』というプロセスを継続的に循環させてゆく必要があるわけだが、このことは学習についても当てはまる。
そうしたプロセスをいかに適切に実行するか、つまりいかにして良い『段取』を組み続けることが出来るかは、勉強においても成否を分ける要因として強く働くのである。よって、その効率化は非常に優先度の高い、取り組む価値のある課題ということになる。
さて、ここで「計画なんて立てても上手く行ったためしがない。どうせ計画通りになんて進まないのだから、時間の浪費でしかない」という反対意見を持つ者もあろうかと思う。しかし『計画を策定すること』は重要である。それに取り組むことで初めて課題がはっきりすることもあれば、必要がないことが明確になることも、「現実的に達成が難しい」ということが判明することさえある。『Plan(すでに策定された計画)』が役に立たないことは多々あれど、『Planning(計画を策定すること)』は非常に高い価値を持つのだ。
もちろん、ことが「計画か実行か」の二者択一であるならば、『実行』に軍配を上げざるをえない。しかし、両者は相互補完的である。「あちらを立てればこちらが立たず」ということにはなりえない。多少面倒でも必ず取り組み、先々で道に迷わず進み続けられるよう、あるいは迷っても正しい道に自力で戻って来れるよう、自分だけの地図を己の力で描くすべを身につけよう。
習熟の極意
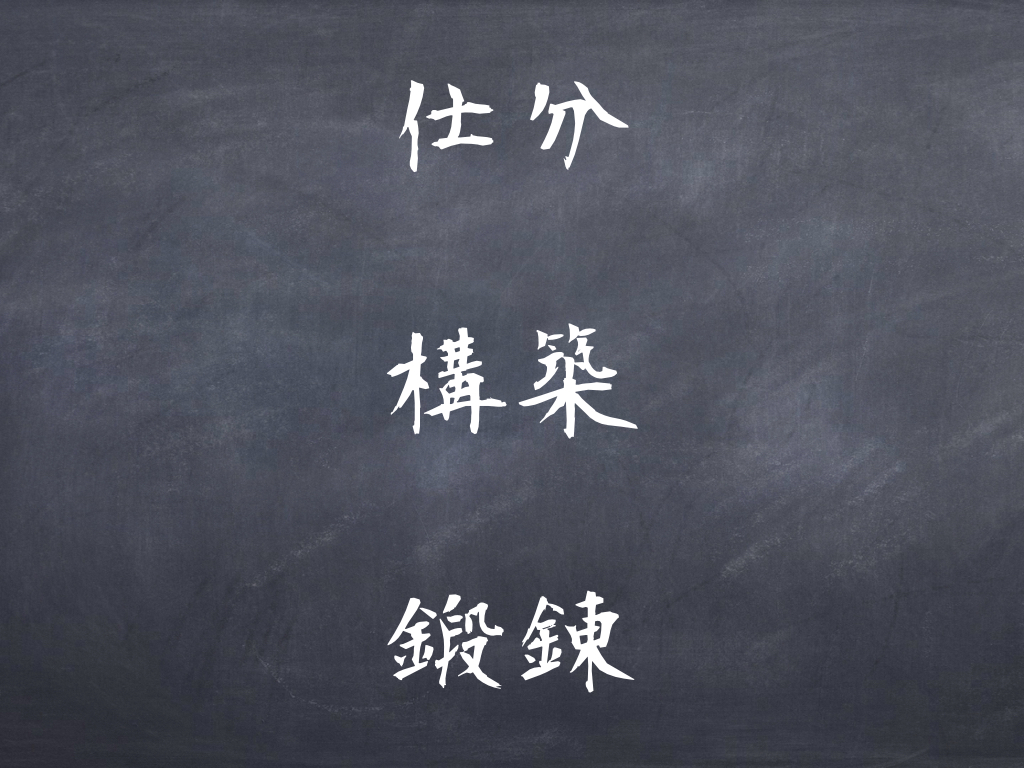
現時点の自分にとって『実現可能かつ最短ルートの計画』を立てたら、次はいよいよ実際に学習を進め、学習対象を自在に扱えるようにしてゆく段階、すなわち『習熟』のプロセスに入る。
ところで、不慣れな学習者の中には、一冊のテキストを完璧にする必要に迫られたとき、「解説の意味がわからないのに、それを強引に機械的暗記しよう」とする者や、もっと酷いと「解答根拠を無視し、正解のみを覚えよう」とする者が現れるが、このような姿勢で取り組んでいるうちは「すでに保持している知識で解けるはずの問題も、ほんの少し外見が変わっただけで解けなくなる」ということが頻発するし、それらの無理やりにでも頭に放り込んだはずの『正解』ですら、その大半がほんの数時間のうちに消えてなくなってしまう。
我々が求めているのは、脳裏から剥がれ難く、仮にそうなったとて、それ以降の記憶の再定着が容易に可能である、そのような概念・知識であるはずだ。では、そうした目的に叶うよう、未知の知識を加工するには、どのような方策をもって臨むべきだろうか?青稲塾では、概念・知識を本当の意味で自分のものにするには、以下のように大きく三つの段階を踏む必要があると考えている。
第一に、日々絶え間なく滝のように降り注ぐ未知の概念・知識について、その習熟度を基準に『仕分』を行うことで、『今なすべきこと』に意識の焦点を絞ること。
第二に、そうした初めて相対する概念・知識と、その周囲に存在する知識との関係性を整理する過程を通し、知識間の『構造』を自己の内に『構築』すること。
第三に、思考の土台として『自在』に活用することを可能にすべく、様々な状況設定や環境で繰り返し使用してゆく中で徹底的に『鍛錬』し、体に深く浸透させることである。
こうした試練を乗り越え、自己の常識とした知識こそが、「いざ!」という時の頼れる相棒となるのである。読者諸君にはこの章を参考に知識に『習熟』する際の要点を押さえ、ぜひとも優れた相棒を数多く味方に揃えて欲しい。
定着の極意

話の都合上最後に触れることになってしまったが、実は効率向上のための三要素の中で最重要なのが、この『定着』である。
というのも、計画通りに進んでいなくとも、知識の整理が適切になされていなくとも、必要な瞬間に必要な知識が頭に残っているのであればその問題は解けるわけだが、それに対し、いくら適切な『段取』を行い、丁寧に『習熟』のプロセスをなぞったとしても、忘れてしまえばどうしようもからである。
その上、君が今痛感しているように、忘却は我々人間のサガである。関連知識とのリンクを張り巡らせ『習熟』した知識でさえ、長時間復習しなければ自在に取り出すのは難しくなってゆくし、さらに厄介なことには、他の知識との関連付けが難しいがゆえに、保持し続けることが本質的に難しい知識もまた存在する。
では、どう対処すべきか?
第一に、一回一回の学習効果を高めるべく『集中』の質を向上させる方法について学ぶこと。
第二に、長期定着率に最大の影響を及ぼす『復習』の質を向上させる効果的な方法について学ぶこと。
第三に、長期記憶化と日中の頭の冴えに大きな影響を与える『睡眠』の質を向上させる方法について学ぶこと。
そして、これら三つを基盤に自己最適化した、より良い行動規則をまとめ上げ、それを常日頃から徹底し、やがて無意識の習慣とすることである。
この項では、知ればすぐ出来る、定着力向上の助けとなるちょっとした工夫を、個別具体的に複数提示してゆく。ぜひとも、なるべく多くのコツを習慣として取り込んでほしい。
まとめ

さて、まとめに入ろう。まず、我々の『目的地(仮)』は『目標達成に対して十分な実力を期日までに養成すること』である。
そのためには『可処分時間』を増やし、『効率性』を改善することが求められる。そして、『効率性』を向上させるには、学習段階を『段取・習熟・定着』の三つに分けた後、さらにそれら三要素をそれぞれ三項目ずつの手法に下位区分し、これら合計九つの方向性から学習行動を改善、全体としてのスタディスキルを抜本的に改革すること。まさにこれこそが、我々のゆくべき道である。
分析
計画
修正
仕分
構築
鍛錬
『定着の極意』
集中
復習
睡眠
・・・というわけだが、さて、当シリーズに興味を持ってくれた読者諸君に注意してほしいことがひとつある。
『自学の極意』シリーズをすべて読み終えたら、ぜひともその日のうちにそれらを実践すべく歩み始め、そして徹底して継続してほしいのである。
というのも、君がこのシリーズを読み終えた時、きっと「なるほど!そうすればいいのか!!」といくらかの気づきを得、その結果、自分が多少高級な存在になったと、ある意味で慢心してしまうことがあるかもしれない。たしかに「やり方がわかった」という分だけ、何も知らないよりは多少ましではあるが、しかし、それは「知識の身につけ方がわかっただけ」に過ぎず、すなわち、読了時点で君が実際に進んだ距離、志望校の問題を解くために身につけた知識は紛うことなき0なのだ。だから、本当に重ね重ねになるが、言わせてもらいたい。重要なのは・・・
『即日実践・徹底継続』である。
筆者は、当シリーズが読者諸君の夢に接近する一助になることを切に願うものである。ぜひとも、夢を叶えるための足がかりとして、一連の記事を有効活用してほしい。
