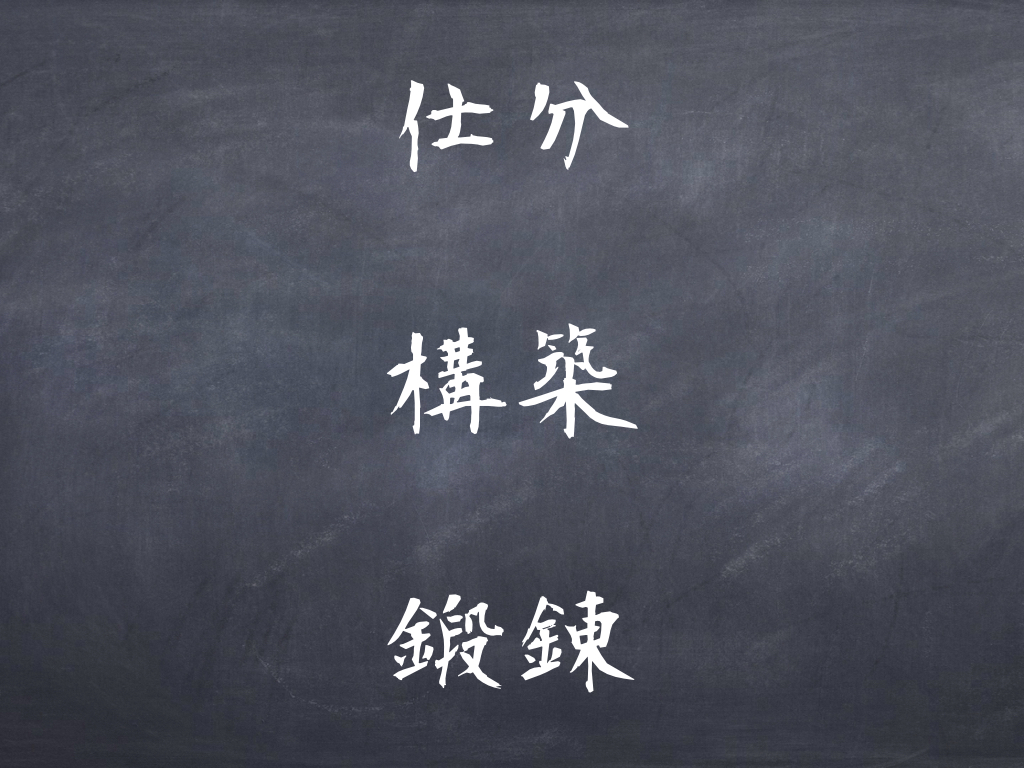
ここまで主に学習の準備段階(『段取』)について詳述してきた。次はいよいよ知識を実際に学び・身につけてゆく局面、すなわち『習熟』について解説してゆく。
習熟度を基準に学習対象の『仕分』を行い、知識間の『構造』を自己の内に『構築』し、『思考の土台』として『自在』に扱えるよう徹底的に『鍛錬』しよう。
『仕分』(習熟の一)
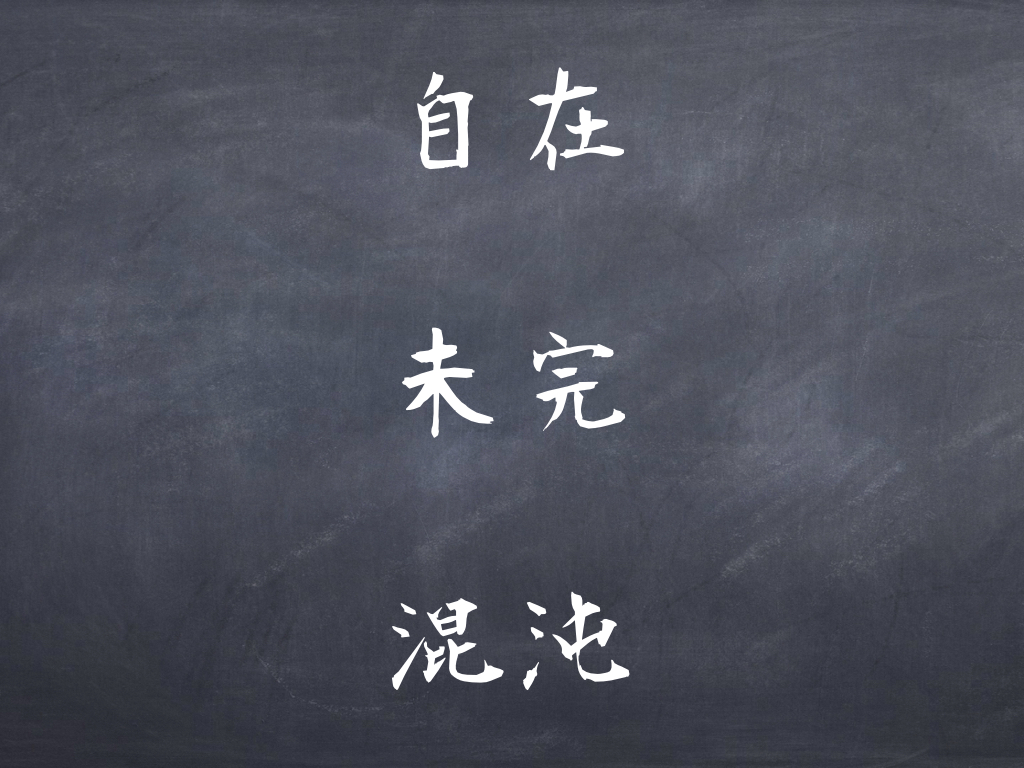
短時間で多くの知識に親しむために必要なことは、まず第一に『なすべきこと』と『それ以外』とを適切に切り分け、そして第二に『なすべきこと』に『可処分時間』の多くを注ぎ込むことである。
『構造化・自在化』の達成を物差しに学習対象を『自在・未完・混沌』へと振り分けること(『仕分』)を通し、『今なすべきこと』に『焦点』を絞る準備を行おう。
『構築』(習熟の二)
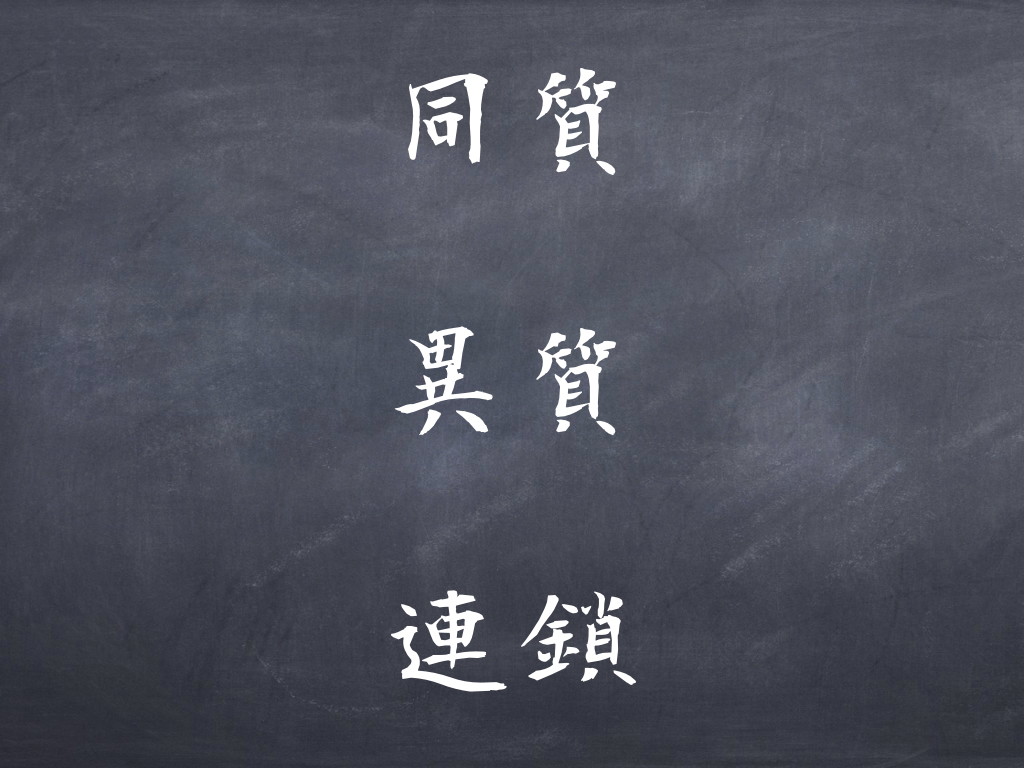
学習対象の『仕分』を無事終わらせることが出来たら、次に行うべきは『混沌』に規則を与えることである。
『同質・異質・連鎖』で『問い』を立て、学習対象と既有知識との関連性を整理することによって、知識間に存在する『構造』を自己の内に『構築』しよう。
『鍛錬』(習熟の三)
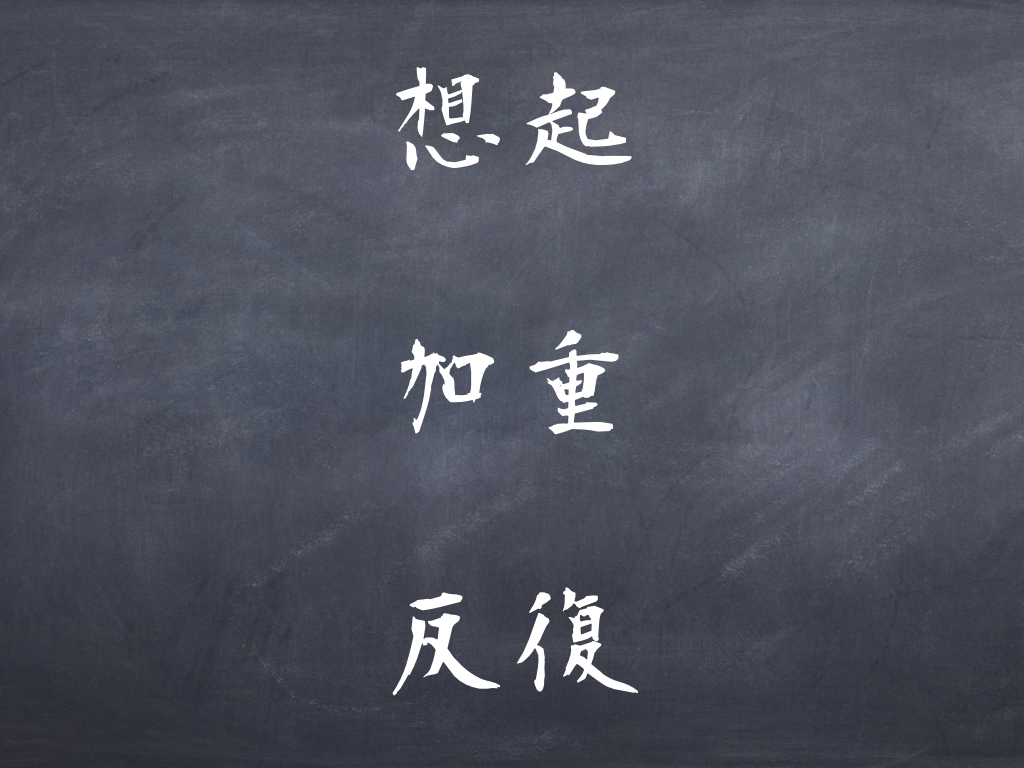
ひとたび関連項目との『構造』を把握した知識・概念といえど、必要な時に『思考の土台』として機能するにはさらなる『鍛錬』が不可欠である。
理解はすれども、完璧とは言い難い、そのような『未完』の知識については、『想起・加重・反復』を合言葉に質の高い再現訓練を施すことで『自在』に働く頼れる相棒として鍛え上げよう。
