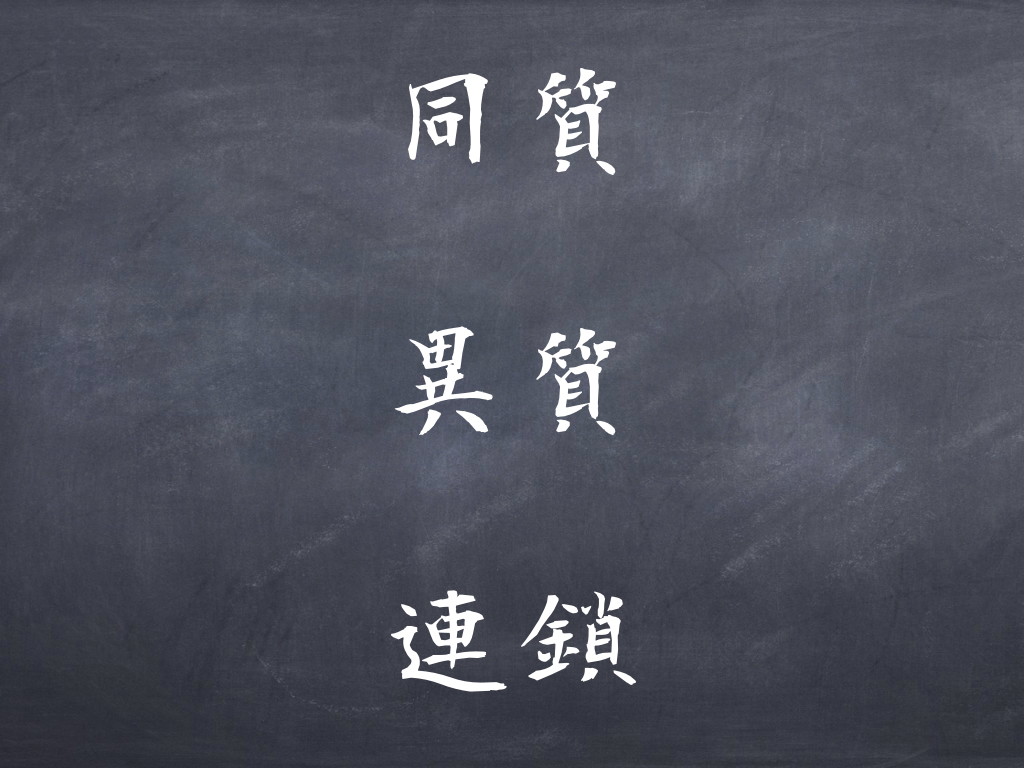
『同質』(構造の一)
対象についての理解を深める方法の一つめは『同質性』による関連付けである。ところで、我々が学ぶべき対象は様々である。それらの概念は・・・
- 国語
- 英語
- 数式
- 図形
- 表
- グラフ
- イラスト
- 音声
・・・などの形で『表現』されているわけだが、『同質性』による『構築』の方法とは、そのように表現された対象と『=』で結びうる表現・概念を探し出し、それらと関連付け、対象についての新たな洞察を得ることによって学習対象への理解を深めてゆく方法と考えてほしい。
では、そうした『=』でつなぎうる概念を探し出すには、どのような方策でもって当たれば良いのだろうか。ここでは、以下の『問い』が役に立つだろう。
- すなわち?
- どういうこと?
- どんな意味?
- たとえると?
- 和訳すると?
- 数式にすると?
- 図形で表すと?
- グラフにすると?
- イラストにすると?
- 音声化すると?
- たとえば?
- 詳しく言うと?
- 例を挙げると?
- 具体化すると?
- 実際に使用される状況は?
- 同じ性質を持つ仲間は?
- 想定しうる可能性は?
- 最大値と最小値は?
- つまり?
- 要するに?
- まとめると?
- ざっくり説明すると?
- 抽象化すると?
- 本質・核心は?
- 共通点を抽出すると?
- 相違点を省くと何が残る?
不慣れな概念に出会ったときには、以上の『問い』を参考にして、対象を新たな方向から見直してみよう。
さて、それでは上記の『問い』を実際どう使えばいいのか具体例を上げてみよう。たとえば、君は今まさに単語暗記の真っ最中で、どのようにしてもcomprehensiveの和訳が覚えられないとする。すると、なすべき行動は以下のようになる。
- comprehensiveの和訳は?
単語集には「包括的な」と記載 - aという日本語の意味は?
国語辞典には「全体をおおっているさま」と記載 - イラストにすると?
画像検索してみよう
自分で描いてみるのも可 - 音声化すると?
付属音声or電子辞書等で確認
その後自分でも発音してみる - 例を挙げると?
辞書には以下の記述があった
“a comprehensive study”
「包括的研究」
“a comprehensive win”
「完勝」 - 同じ性質を持つ仲間は?
英英辞典を引くと類義語として以下の単語が紹介されていた
thorough
full
complete
wide
extensive
こんな塩梅である。多義語の攻略には、以下の問いが使えるだろう。presentを例に取る。
- presentの意味は?
- 和訳「a,b,c」の共通点は?
- 本質・核心は?
P’
ちなみに、数学分野において公式の導出過程や解法を覚える際には、以下の問いが便利だろう。
- 導出過程にある数式の意味は?
- その数式を図形で表すと?
- 与えられた数式に具体的な数値を代入すると?
- その結果をグラフにすると?
- 最大値と最小値は?
- ざっくり説明すると?
もちろん、場合によっては今回使わなかった『問い』を使うこともあるだろうし、他にも、『異質性』や『連鎖性』を梃子にして情報を加工し、忘却を遅らせることもあるだろう。
未知の概念・納得のいかない説明・覚えづらい知識に出会ったときには、まずはこうして自己に問いかけ、それに対する答えを考えたり、辞書や参考書などで調べてみることを強くおすすめする。
一般的に、学習の成否を分ける要因としてとりわけ強く働くのは、いかに能動的に知識を獲得するよう努めるかという、前向きな学習姿勢の有無である。くれぐれも思考停止の機械的丸暗記は避けよう。
『異質』(構造の二)
対象についての理解を深める方法その二は『異質性』による関連付けである。学習対象と『≠』で結びうる概念を探し、それと関連付けることによって学習対象への理解を深める手法であるが、そうした『≠』でつなぎうる概念を探すときには、以下の『問い』が役に立つ。
- 単純な要素に還元すると?
- これは何であり、何でない?
- これとあれの境界はどこ?
- 対極にある概念は?
- 逆の目的を持つ概念は?
- 混同されやすい似て非なるものは?
- それらの間にある共通点は?
- 共通点を省くと何が残る?
- もしXでなかったとしたら?
- ありうべく理想状態は?
- 理想状態の妨害要素は?
- これがなければ何が起こる?
- 規則性・対称性・単純性を高めると?
これらの『問い』を英単語暗記に活かすのであれば以下のようになるだろう。今、adaptとadoptをどうしても混同してしまうとする・・・。
- 混同されやすい似て非なるものは?
adaptとadopt - それらの間にある共通点は?
ad - 共通点を省くと残るのは?
aptとopt - aptの意味は?(『同質性の問い』)
「〜しがちな・ぴったりの」と辞書に掲載 - optの意味は?(『同質性の問い』)
辞書で探したところ「〜の方を選択する」と載っていた。 - aptの仲間は?(『同質性の問い』)
不明 - optの仲間は?(『同質性の問い』)
Google検索の結果、option「選択」が仲間らしいことが判明
ここまで来れば、今後この2つの英単語を混同してしまうことを防げるだろう。
もちろん英文法に応用することも出来る。たとえば、「もし金持ちだったら、世界中を旅行できるのに。」という仮定法の文を作りたいとする。その場合には、以下のように考えてはどうだろうか。
- 仮定法と対極にある概念は?
直接法 - それらの間にある共通点は?
両者とも、法(話し手の主観・考え方・認識)を表す - 共通点を省くと残るのは?
直接法は現実を表し、仮定法は仮想を表す。
直接法は時制を普通に用いる。(現在のことは現在形で、過去のことは過去形で)
仮定法は時制を過去にずらす。(現在のことは過去形で、過去のことは過去完了形で) - もし仮定法でなかったら?
「もしお金持ちだったら、君も世界中を旅行できるだろうに。」という文を仮に直接で書くとしたら・・・
“If you are rich, you can travel around the world.”となる
本当は仮定法の文なので・・・ “If you were rich, you could travel around the world.”
このように、時制を一つ過去にずらして完成!
数学に関しても同様である。たとえば、恒等式がイマイチよくわからない場合であれば、以下のように考えてはどうか。
- 混同されやすい似て非なるものは?
方程式 - 共通点は?
両者とも等式である - 違いは?
恒等式は変数がなんであれ成り立つ
方程式は変数が特定の値のときに成り立つ
つまり「普遍と特殊」 が両者の違いである
よって、恒等式に関しては係数比較法が可能
合同条件を覚えている中学生が相似条件を覚えるには以下のように考えると、覚えが早いだろう。
- 混同されやすい似て非なるものは?
三角形の合同条件 - 共通点は?
条件が三種類あり、それぞれが以下のように対応
①三辺についての条件(三辺相当と三辺比相当)
②二辺狭角についての条件(二辺狭角相当と二辺比狭角相当)
③二角についての条件(一辺両端角相等と「二角相等」) - 違いは?
合同条件ではカタチだけでなく、大きさも同じであることが保証されるが、相似条件が保証するのはカタチのみで、大きさが同じであることは保証されない
よって、①と②のように「辺の長さ」が「辺の比」に変化するが、三角形においては二角相当であれば、結果的に三角相当であり、カタチが等しいことが保証されるので③のように変化
『連鎖』(構造の三)
対象についての理解を深める方法その三は『連鎖性』による関連付けである。学習対象と『→』で結びうる概念を探し、それと関連付けることによって学習対象への理解を深める手法であるが、そうした際には、以下の『問い』が役に立つ。
- それは何からつながるか?
- それは何へとつながるか?
- それらは何がつなげるか?
上記の『問い』は以下のように言い換えることもできる。
- 始点は?
- 終点は?
- 中継点は?
あるいは・・・
- 前提・仮定・条件・原因・理由は何か?
- 結論・帰結・結果は何か?
- 隠れた前提はないか?
・・・である。他にも以下の『問い』も『連鎖性』に着目したものであると言えるだろう。
- それはなぜ使えるのか?
- それはどう使えるのか?
- 部分から全体を考えると?
- 全体から部分を考えると?
それでは実際にやっていこう。たとえば、considerという単語の意味がどうしても覚えられないとしよう。その場合には、以下のように考える。
- それは何からつながるか?
considerの語源を調べ、「conはtogether、siderはstarを表す」ことがわかった。
つまり、considerを語源的に考えると「星と一緒に」となるようだが、ここで一つの謎が生まれる。
なぜ「星と一緒に」が「熟考する」になるのだろうか?? - それらは何がつなげるか?
本で調べたところ、西洋において昔は占星術が盛んであったことに由来するらしい。
昔は重要なことについてしっかり考える際に星の運行を参考にしていたのだ。
つまり、「星と一緒に」→「星の運行を参考にすることで熟考・熟慮」→「よく考える」ということのようである。
当然、英文法に使うこともできる。今、助動詞の入った文、たとえば「彼は速く走ることが出来る。」という日本語に対応する英文が正確に作れないとしたらこんなふうにすればいい。
- それは何からつながるか?
文末に「出来る」とあるから、canを使うはず!
前提として、canの入っていない文ならどうなる?
すなわち「彼は速く走る。」ならどうなるか?
He runs fast.となるはず。
これにcanを加えると・・・
He can runs fast.となる - それらは何がつなげるか?
助動詞直後の動詞は原形なので・・・
He can runs fast.ではなく、
He can run fast.となる!
他にもたとえば、ある英文にある「文頭のto不定詞の働き」の判定方法がよくわからないときなどは以下のようにしてはいかがだろうか。
- 終点は?
ここでの用法は副詞的用法 - 始点は?
「文頭のto不定詞が名詞用法でないなら、副詞用法である」と書いてある。
なぜ・・・??
不定詞の用法は名詞・形容詞・副詞の3つじゃないの?
形容詞用法だってあるはずなのに・・・。 - 中継点は?
「文頭のto不定詞は形容詞用法ではありえない」という事実があるのだろうか?
参考書で探してみると・・・
「形容詞的用法の場合は、something to drinkのように、名詞に対して後ろから掛かる」という記述を発見!
だから、文頭のto不定詞が形容詞的用法であることはありえないのか!!
もちろん、数学に活かすこともできる。根拠として述べられていることと、その結論部分の言っていることは理解できるのに、それらのつながり方が上手く理解できずなんとなく釈然としないなんて経験はないだろうか?
